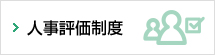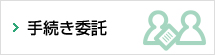試しに落とし穴を探してみる
- 試用期間中または試用期間が終わるときなら、
一方的に辞めてもらっても問題ない。
- 【解説】
試用期間中又は試用期間が終わったからといって、自由に辞めさせられるわけではありません。
試用後14日を経過した場合は、解雇予告あるいは解雇予告手当が必要になってきますし、解雇する理由も必要です。正規従業員の労働契約との違いは、試用期間中の者の労働契約が解約権留保付の労働契約であるという点にあります。つまり、いざという時には正規従業員の解雇よりも広い範囲で解約権の行使が認められるということです。とは言え、何の理由もなく解雇ができるということではなく、客観的、合理的な理由を欠くと解雇権の濫用ということになりますので、注意が必要です。
- 退職するときにトラブルになりやすいのは仕方がないことだ。
- 【解説】
退職の意思表示は、「退職の申し込み」と「辞職の意思表示」の2つに区分することができます。
「退職の申し込み」によって退職するためには、会社がそれについて承諾することが必要になります。(合意退職と呼ばれます)
一方「辞職の意思表示」は、労働者からの一方的な契約解消行為であり、会社の承諾は必要ないことになります。
やはり会社としては、引継業務が不完全なままに退職されてしまうことはリスクですから、できれば会社と労働者本人が合意の上で退職日を設定することが望ましいと思います。
会社の望む退職日を設定し、退職に伴うリスクを軽減するためにも、就業規則には、「合意による退職」と「辞職」を区分して規定して、「合意による退職」と「辞職」について、退職金額に差をつけることも、合意による退職を労働者に促すためには、有効な手段だと思います。
- 私傷病による休職規定には、特に手を加える部分はない。
- 【解説】
昨今の精神疾患(いわゆるうつ病)の発生頻度が劇的に増加しているという現状も踏まえて、休職事由を規定していくことが効果的です。
「前各号のほか、特別の事情があり休職させることを適当と認められるとき」という項目により、精神疾患の労働者に対しても対応は可能と言えますが、現在、精神疾患は特別の事情ではなく、普通に起こり得ることであるという認識を持つことが大切です。また漠然と「必要な期間」と規定しておくことは、上限が不明瞭となって休職期間が長期化する危険性があるので避けたいです。
他にも、「私傷病による欠勤が引き続き1ヶ月を超え」という欠勤日数が休職の要件となっていることが多いですが、精神疾患患者は、身体的疾病とは異なり、欠勤するにしても、必ずしも連続して欠勤するとは限りません。出勤、欠勤を繰り返すというケースも多々あります。
また、特に精神疾患の場合においては、欠勤の要件を充足するには至らなくても、明らかに通常の労務提供が困難(不完全)であるという事態も、十分に想定されます。そういった事態に対応するための休職事由を追加するとよいでしょう。会社の判断により、速やかに休職命令を発することができるということは、業務による症状の悪化を防止するだけでなく、不完全な労務提供を会社が受領することによるリスクを回避することが可能となります。
- 業績も良くないから、昇給は当然中止している。
- 【解説】
給与の改定は、就業規則に基づいて行うもので、就業規則の定めが、「会社は、毎年1回4月に社員の給与の見直しを行う」などと、昇給、据え置き、降給、いずれのパターンも想定した定め方とされている場合には、事情を踏まえたうえであれば問題ないでしょう。
しかし、「昇給は、毎年1回、4月に行う」などと、昇給することを前提とした定め方をしている場合には、就業規則違反となる可能性があります。もし、就業規則が後者のような定めになっていて、それでも賃金を据え置かざるを得ないのであれば、従業員の同意を得る必要があります。この場合、賃金の据え置きが雇用を維持するためにはやむを得ない措置であることなど、昇給できない理由とともに、今後の見通し等についても十分説明し納得してもらう必要があります。
なお、就業規則を作成していない事業場などで、これまで慣行的に、毎年、いくらかずつでも必ず昇給している場合に、賃金を据え置くときには、その事情などについても、同様に扱う方がよいでしょう。
- 従業員から復職を願いでてきたら認めることにしている。
- 【解説】
休職でも触れましたが、多くの就業規則の休職規定が、身体的疾患を想定しているという現状があります。そして、その休職の規定に対応して、復職の規定についても、身体的疾病を想定していることがほとんどです。しかし昨今は、身体的疾病よりも精神的疾病の方が、会社にとってリスクが高いという事情は、説明した通りです。
ですから、原則として、精神疾患になった場合については、速やかに休職させて、復帰できるような状況にまで回復できなければ期間満了とともに退職となる流れを、仮に復職させるとしても、そのハードルを上げておくことを、規定化しておくことが極めて重要になるのではないかと考えます。
また、復職できるか否か判断するためには、医師の診断書は必要不可欠と言えますが、復職の判断の主体は、あくまでも会社側にあるという認識を持って頂かなくてはなりません。
医師の診断書は、あくまでも医学的見地からの判断であり、医師が会社で労働者がどのような業務を行っていたのか、そして業務にかかる負荷はどの程度なのかまで考慮した上で、診断書を書いているとは到底思えません。休職を判断したのも会社である訳ですから、復職を判断するのも会社であって然るべきであり、医師の診断書を判断材料の1つとして、最終的には会社の判断で復職を許可するということが重要です。
医師の診断書に疑念が残る場合には、直接医師に問い合わせをすることや、会社の業務をよく理解している産業医に診断を受けることができる体制づくりも必要になってくるのではないかと思います。
- 退職金を支給した後に懲戒事由が発覚した場合には、当然返還を請求できる。
- 【解説】
退職金規程に「懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある」と定めている場合は、多いと思います。しかし、これだけでは、退職金を既に支払ってしまった後に懲戒事由が発覚した場合に、退職金の返還を求めることができません。
ですから、例えば「退職後に、在職中に懲戒解雇事由に該当することが発覚した場合、既に支払った退職金については、その金額を返還請求できるものとする」という一文を加えることで、上記の例のような事態が発生しても、退職金の返還を求めることが可能となりえます。
- 営業手当(固定残業代)を払っているのだから、残業代の支払いはしていない。
- 【解説】
割増賃金の支払いは、原則、一賃金支払い期間内に発生した時間外・休日・深夜労働の実労働時間を把握し、割増賃金の単価を乗じて計算します。
しかし、毎月発生するだろう時間外労働等の賃金を、あらかじめ一定の金額を残業代として支払ってしまう方法を固定残業代(手当)とよび、導入している企業も見受けられます。
ここで注意したいのは、現実の時間外労働により発生する割増賃金が、固定残業代(手当)の金額を超えた場合には、その超えた分については別途支給する必要があるということです。
また、この方法の導入に際しては、就業規則、賃金規程などにおいて、その定義や支給要件を明確に定めておくことが必要ですし、従業員へも説明し、理解を得ておくことが重要になります。
景気の変動により、残業時間も以前と比べるとだいぶ減ったということもあります。もし実情に合わせて固定残業代(手当)の金額を見直す必要性があるならば、それについても規定しておくことが必要でしょう。